リハビリの知識・スキルを高める上で、書籍を重宝する機会は多いと思います。
ですが、リハビリ関係の書籍はその数も多く、そして値段も高いですよね…。
また地方に住むPT・OTは、実際に中身を確認できずに口コミ頼みで、ネット通販で購入して失敗した経験はあるあるじゃないでしょうか?
 やまとも
やまともせっかく買ったのに思ったのと違ったってことは多々あるよね
高いお金を払うなら、失敗せずに良書に出会いたいと思うのは誰でも同じですよね!
そこで本記事では、整形外科クリニックで勤務する筆者が臨床を行う中でおすすめの運動器関連の書籍を紹介していきます。
整形外科疾患のリハビリ書籍おすすめ10選
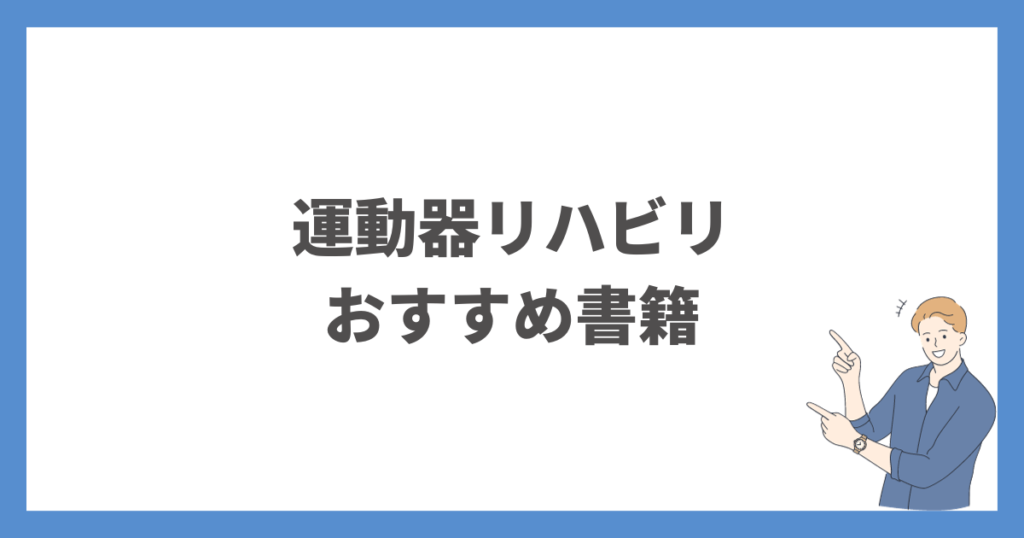
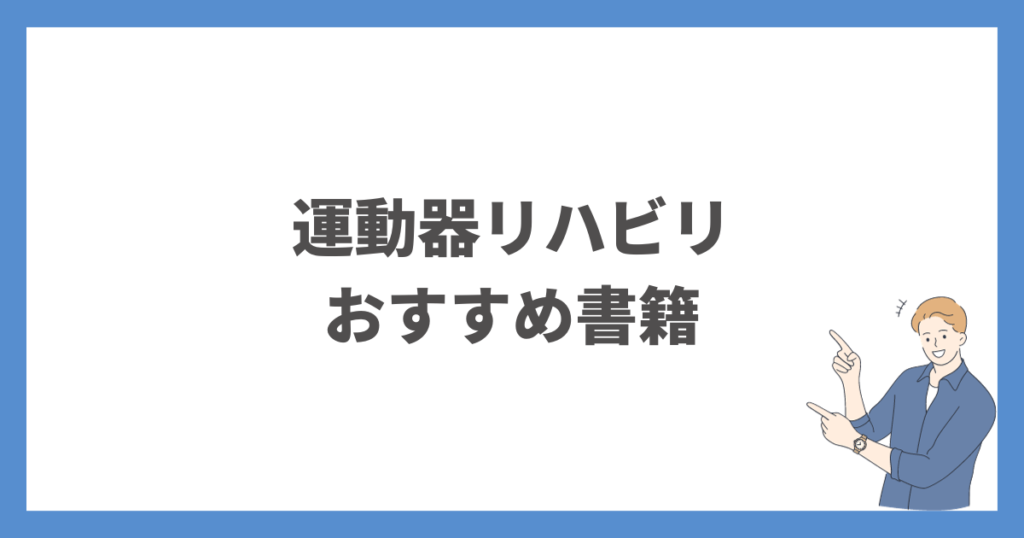
それでは実際に購入して読んでみて、「臨床で使えるな」っと思う書籍を10冊紹介していきます。
どれもおすすめなので、お金は掛かりますが全て持っておくのが良いと思います!
園部俊晴の臨床『膝関節』
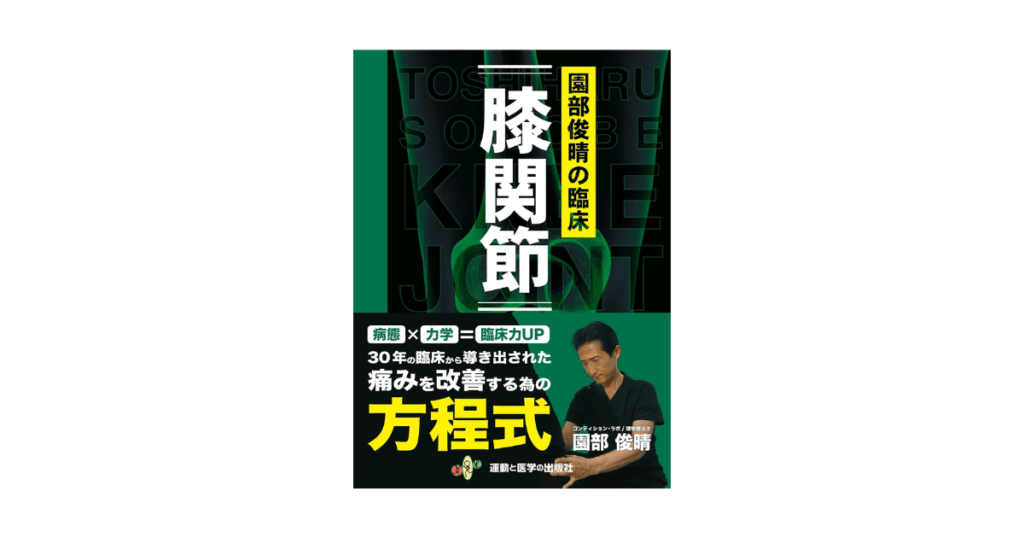
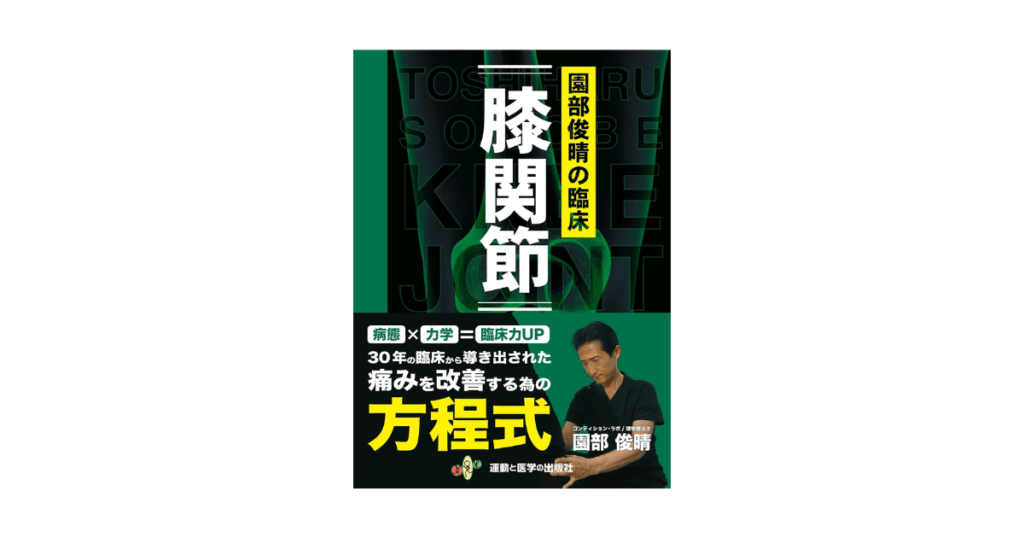
膝関節疾患は臨床の中でも頻繁の遭遇する疾患です。
特に痛みに対する治療がメインになることが多いですよね。
この「園部俊晴の臨床『膝関節』」では、膝関節の痛みで多い組織に関して詳しく病態・評価・アプローチまで解説されています。
膝関節を診る全てのセラピストのバイブルとなると言っても過言ではない一冊です。



僕もこの書籍のおかげで臨床力がかなりアップしたよ
園部俊晴の臨床『膝関節』の詳細は、こちらの記事でくわしく紹介しています。
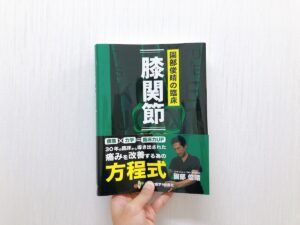
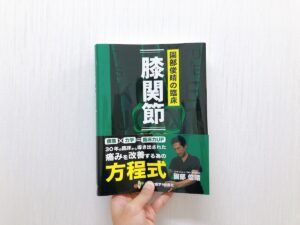
成田崇矢の臨床『腰痛』
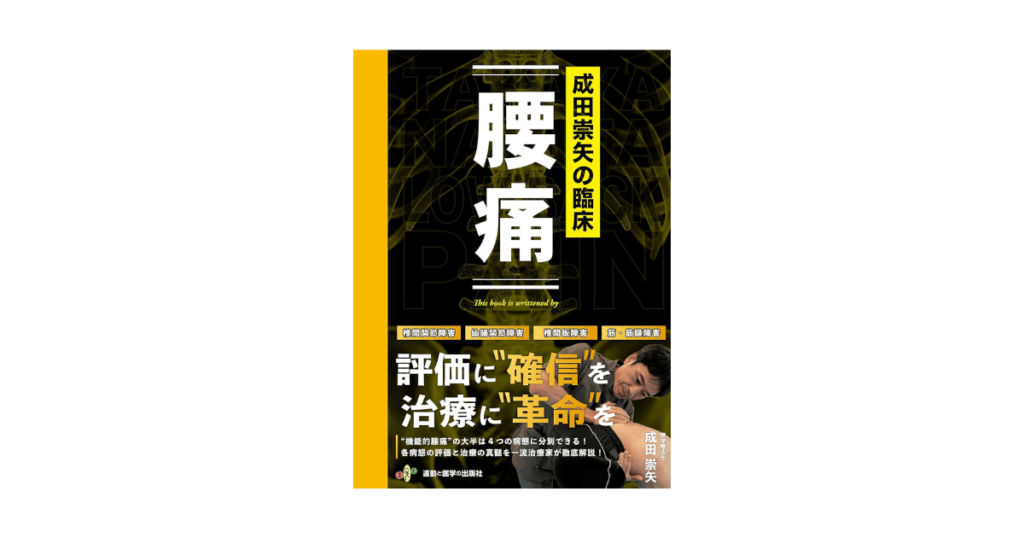
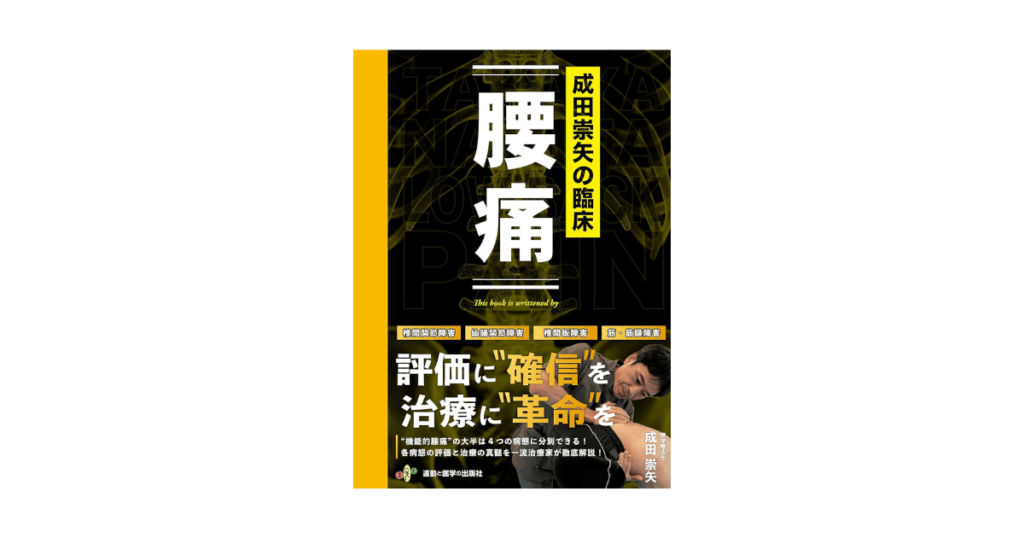
臨床で多い腰痛は、その原因を特定するのが難しく難渋することが多々ありますよね。
「成田崇矢の臨床『腰痛』」は、そんな難解な腰痛の原因を4つの組織に分類して、詳しくい評価・治療アプローチを紹介しています。
写真も多くイメージしやすく、腰痛の原因を探るヒントが多く記載されています。



難しい腰痛のイメージが明快になる書籍だよ
運動器疾患の機解剖学に基づく評価と解釈
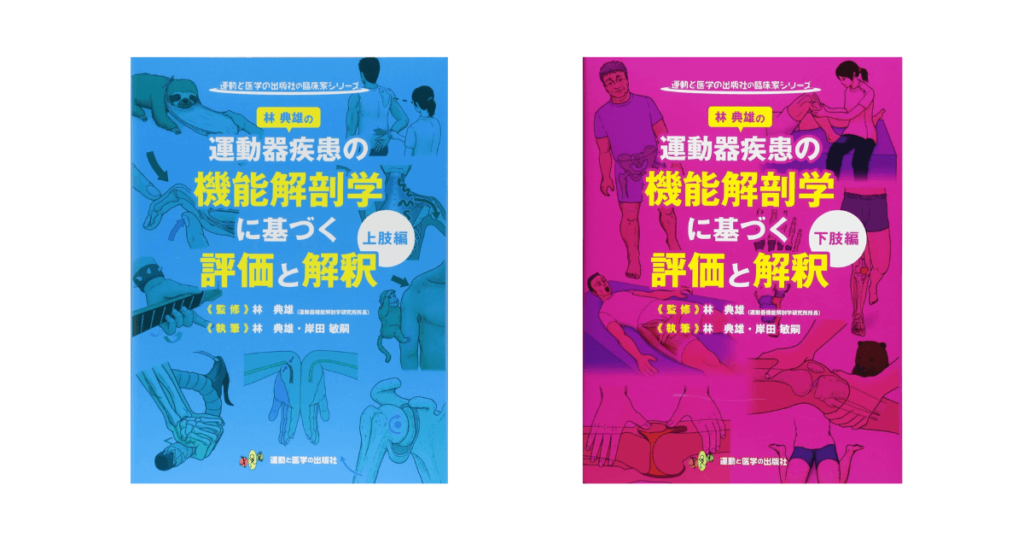
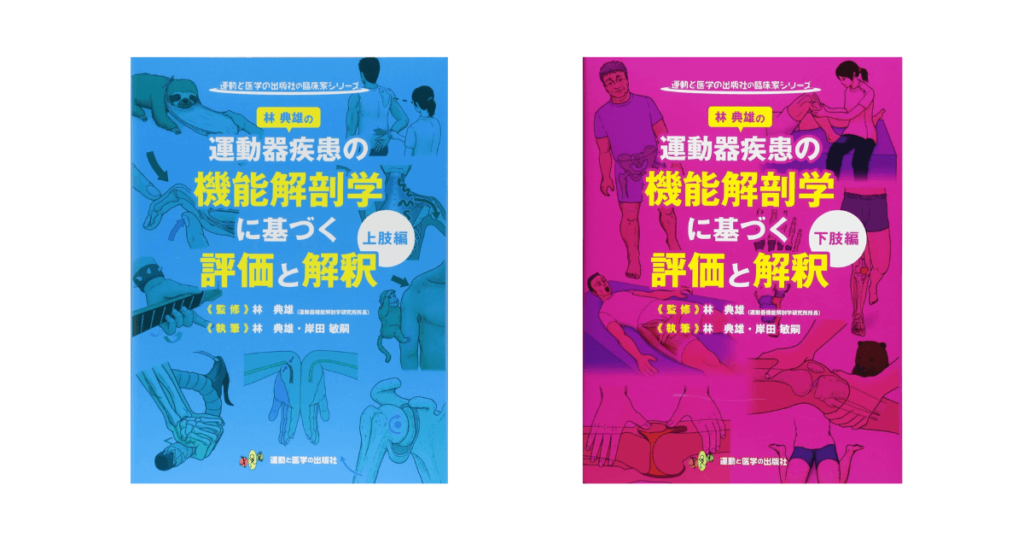
「運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 上肢・下肢編」は、理学療法士の巨匠・林典雄先生の書かれた良書です。
豊富なイラスト・画像を使いながら、各関節の機能解剖や評価方法などが分かり易く解説されています。



上肢・下肢編に分かれていて、各関節のことが満遍なく網羅されているよ
内容も臨床に則していて、「明日の臨床で使える!」と思うヒントが各所に散りばめられています。
新人セラピストからベテランまで関係なく、読み応えのある内容となっています!
イラストもキャッチーで、読みやすいのもおすすめのポイント。
運動器機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略
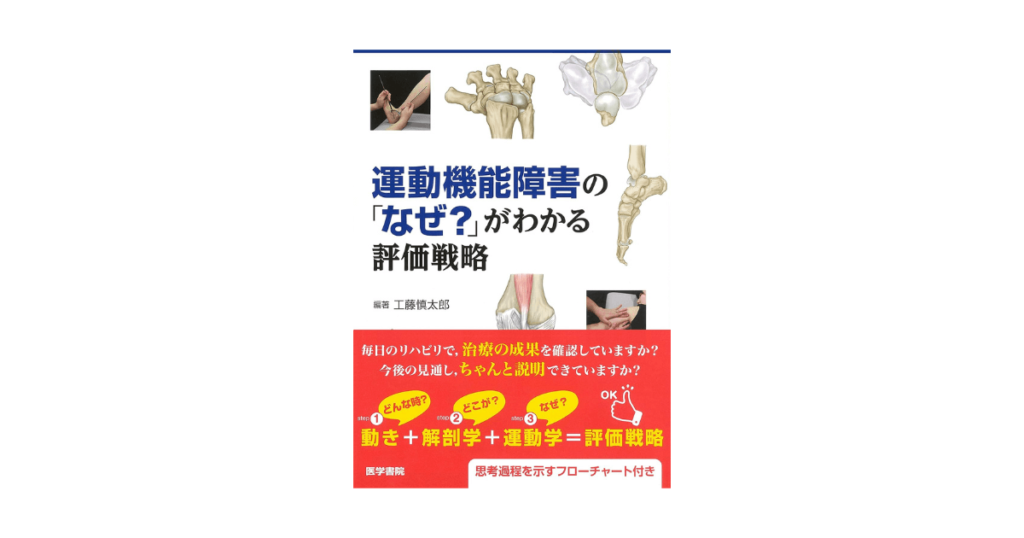
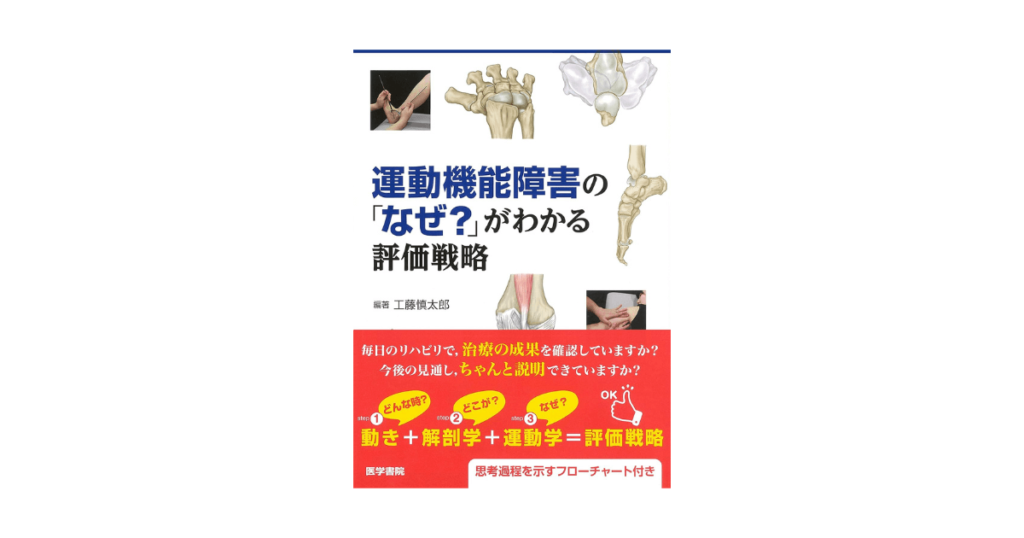
「運動器機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略」は、工藤慎太郎先生が執筆した大人気な書籍です。
運動器疾患に限らず、リハビリを行う際には評価・臨床推論が非常に大事になります。
特に20分1単位の外来では、適切な評価・臨床推論によって最短で問題点の“#1”を見つけ出し、治療→ホームエクササイズの指導まで行わないといけません。
しかしこの評価・臨床推論は非常に難しく、問題点を見つけ出すのに難渋しますよね…。
そういった評価・臨床推論に悩むセラピストに向け、分かりやすく推論の仕方が記載されていて、もの凄く勉強になる一冊です。



疾患の病態も分かりやすく記載されていて役立つこと間違いなし
足部・足関節理学療法マネジメント
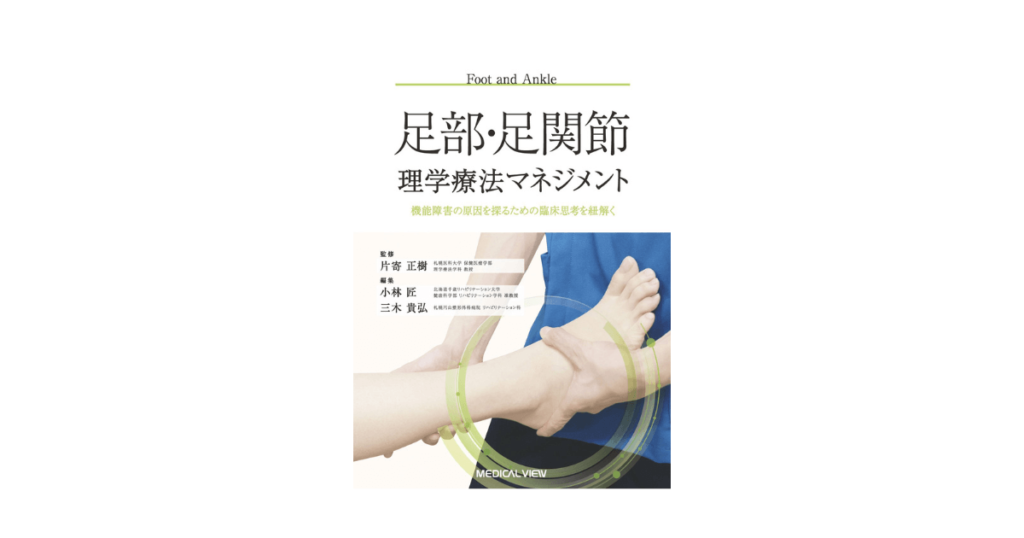
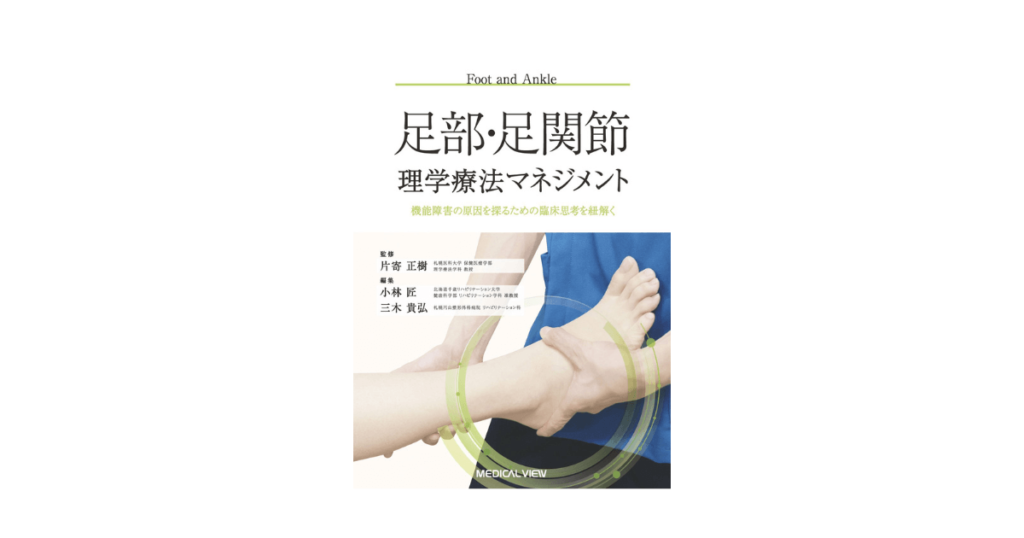
足部のことだけが詳しく書かれた書籍って意外と少なくないですか?
もっと詳しく足部を勉強したいけど、なかなか良い書籍がない…という方にぜひ読んでもらいたいがこの「足部・足関節理学療法マネジメント」です。



足部に関しては、これ一冊で十分ではないかと思うほどの内容量だよ
足部・足関節疾患を担当する機会の多いセラピスト、足部に興味のあるは是非!
肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版
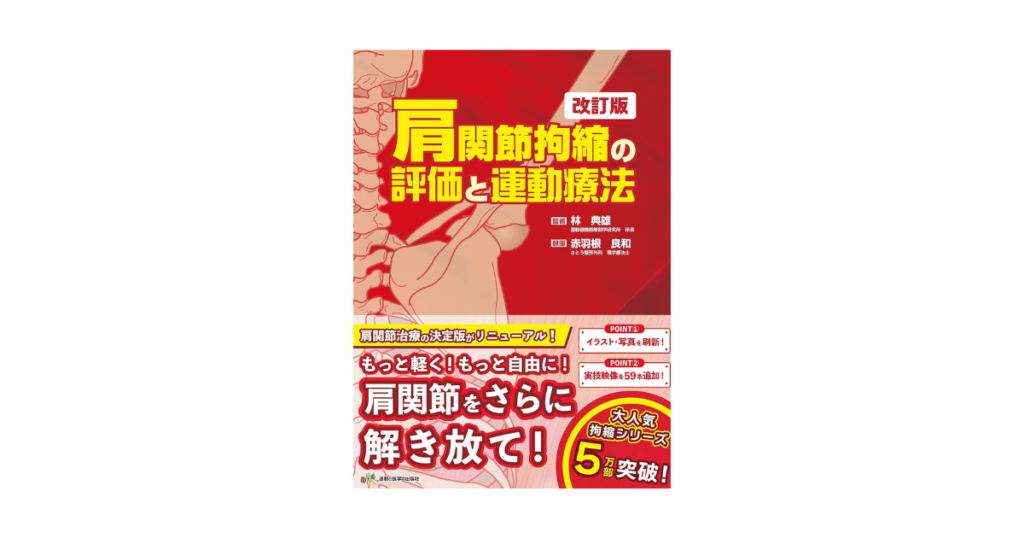
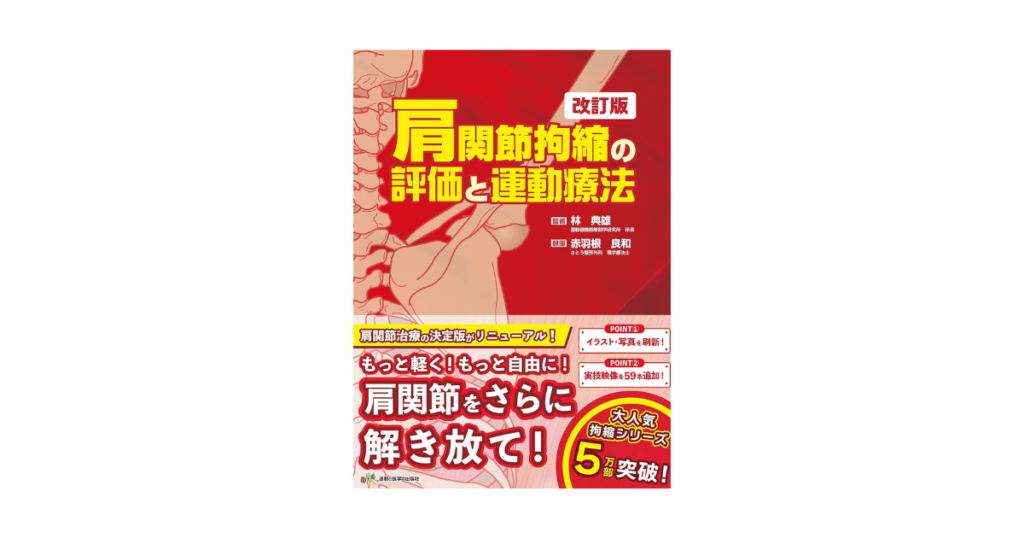
臨床でも肩関節疾患、特に拘縮(凍結)肩には難渋することが多いと思います。
「肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版」では、そんな難渋しやすい拘縮肩への理解を深める機能解剖や病態の考え方が詳しく書かれています。
また実際のアプローチ方法なども各筋ごとに記載されていますので、臨床に即活かせる内容になっています。



著者の赤羽根先生は、セミナーでも受講生から「分かりやすい」と大人気の先生だよ
そんな赤羽根先生が書かれた書籍なので、分かりやすいのは折り紙付き!
肩関節に対して苦手意識のある方は、この本から勉強を始めてみてはいかがでしょうか?
腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック
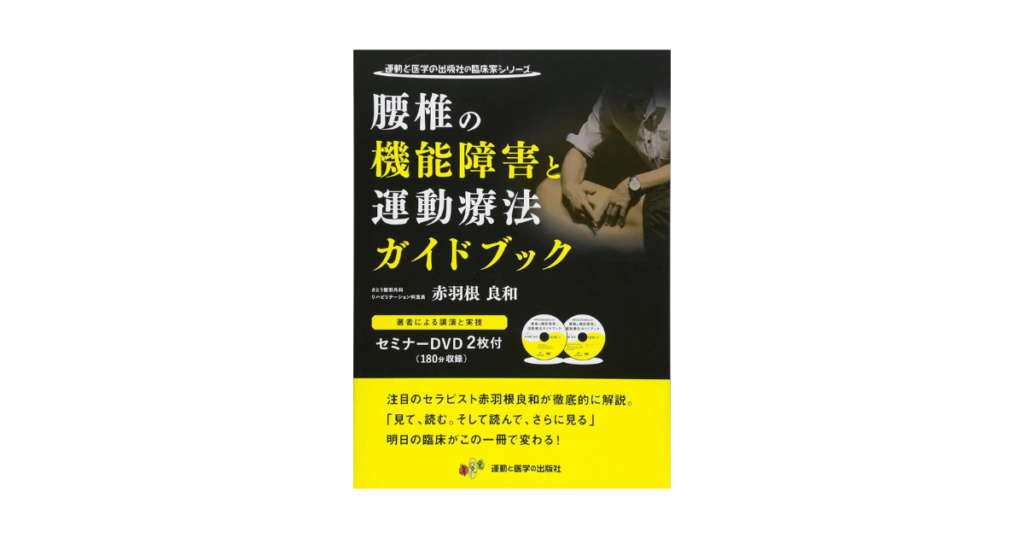
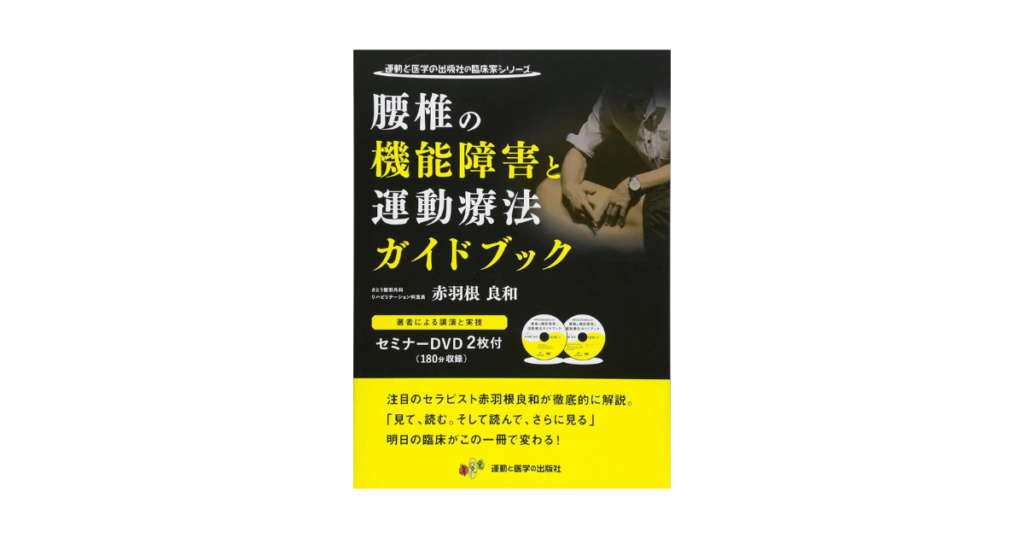
運動器疾患で多いのが腰椎疾患で、若年層から高齢層まで幅広い世代で腰痛(下肢症状)を発症する方は多いですよね。
ただ数は多い分、リハビリで難渋しやすいのも腰椎疾患の特徴。
一括りに腰痛と言っても、年代によって好発の疾患も違いますしアプローチ方法も変わってきます。
そんな腰椎疾患に対応するためのエッセンスが、この「腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック」には詰まっています。



新人セラピストにも分かり易い内容になっていますよ
腰椎疾患の患者さんに苦戦している人には、ぜひ読んで貰いたい良書!
トリガーポイント治療 セルフケアのメソッド
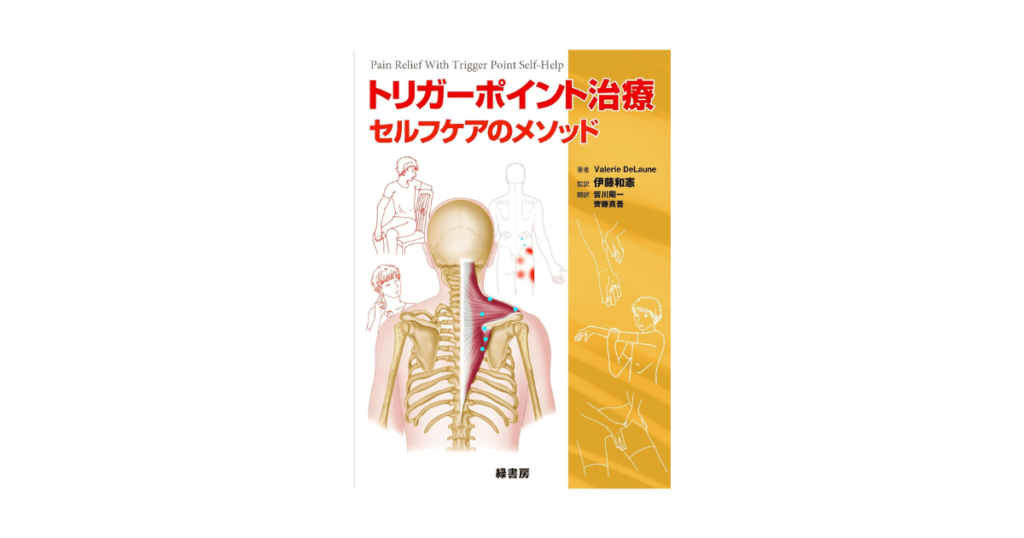
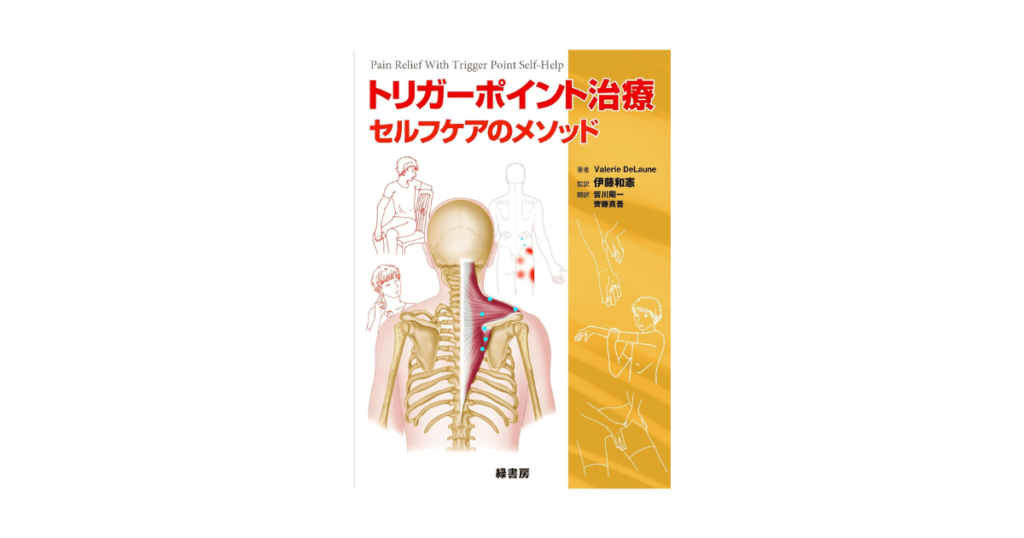
運動器疾患では「痛み」への対応がメインとなることが多いですよね。
疾患の病態や各関節の機能解剖、メカニカルストレスを考慮して、痛みの原因を推論し治療するのは凄く凄く大切。
でも臨床をしていると、トリガーポイントによって痛みが引き起こされているケースも非常に多いのも事実。



トリガーポイントの概念を知らずに、運動器疾患のリハビリを行うことは正直もったいない
トリガーポイントを知ることで、救える患者さんは多くいます。
骨格筋の形と触察法
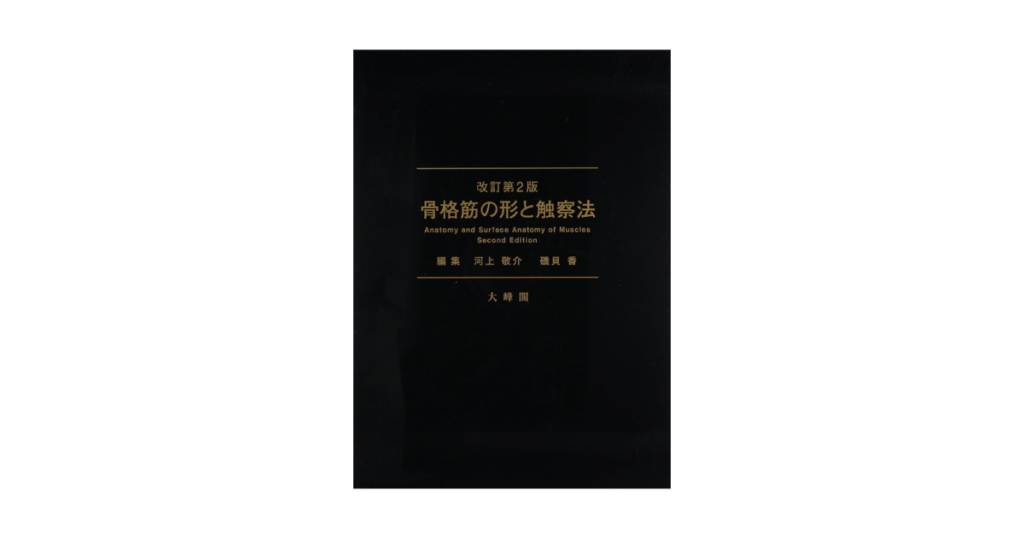
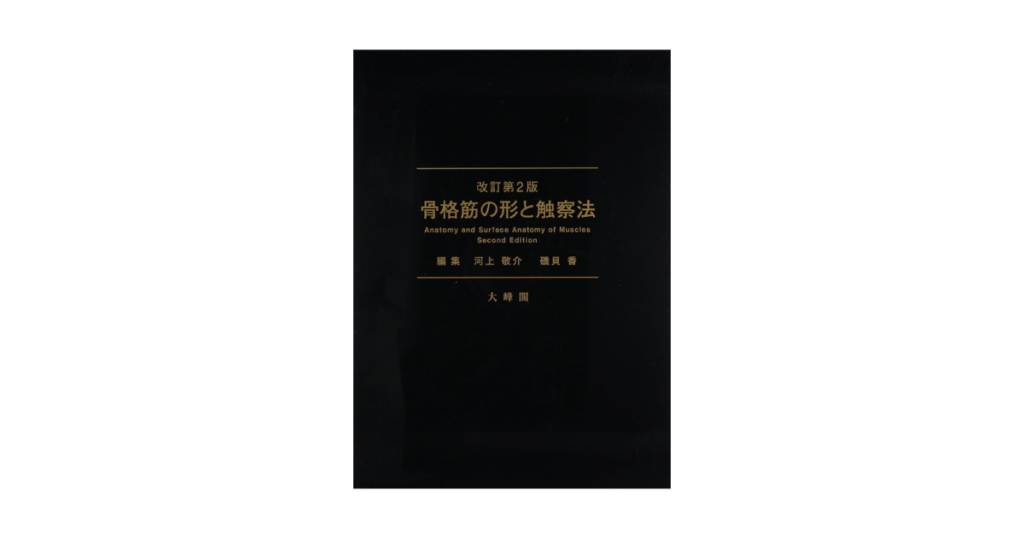
治療の効果を左右する一番の決め手は、どんなテクニックよりも触診力だと感じています。
どんなに効果的なテクニックを知っていても、目的とする組織をしっかりと触り分けられないと効果は不十分です。
最近では人体解剖の分かりやすいアプリもありますが、この書籍ではご献体の写真が多く載せられており、リアルな筋と筋の連結や走行などがしっかりと学べます。



確かな解剖の知識があることで、治療のアイデアも浮んできますよ
少しサイズの大きな書籍ではありますが、全セラピストに必見の良書と言えます。
超音波でわかる運動器疾患−診断のテクニック
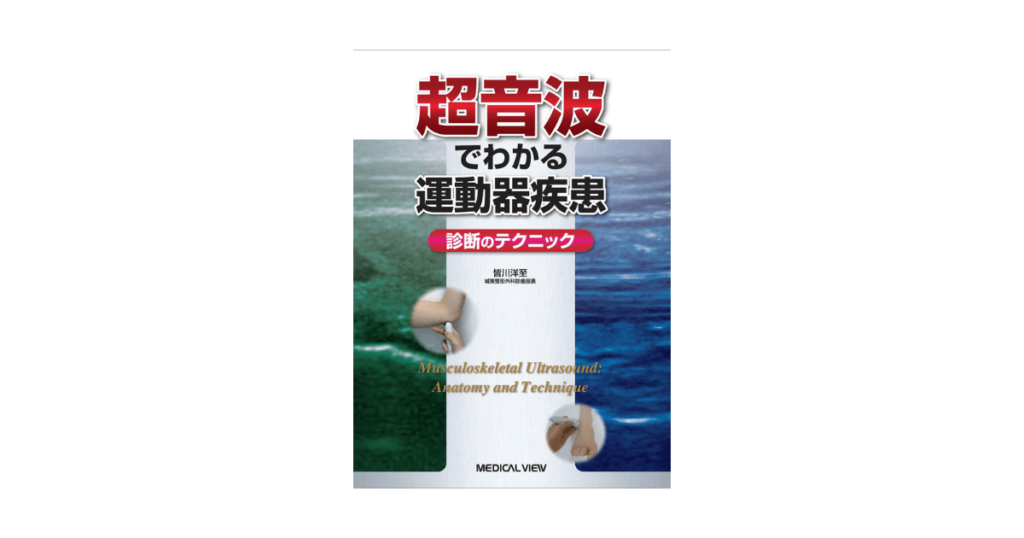
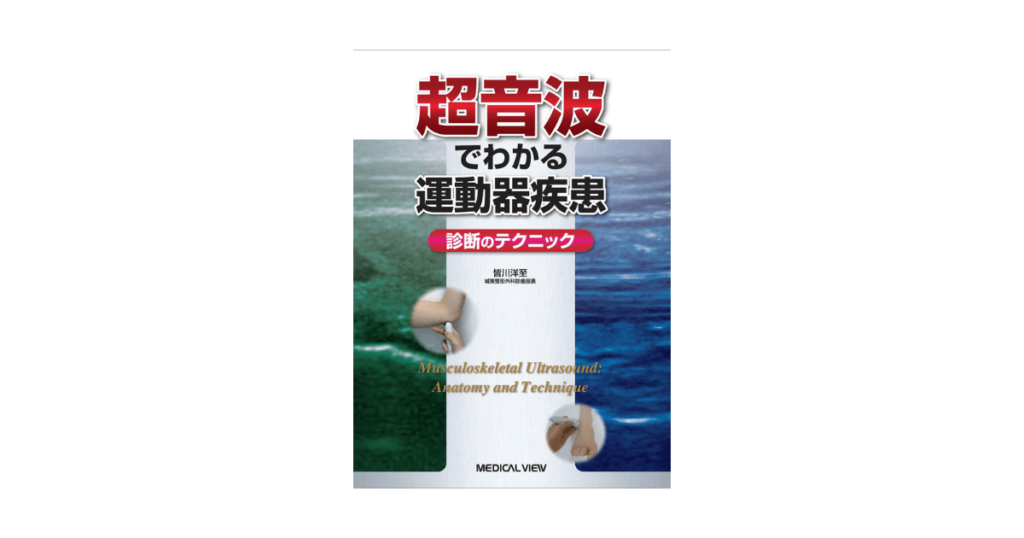
近年では運動器疾患にエコーを使って、病態把握・治療を行うのがトレンドになっています。
ただエコーは慣れるまでが難しく、ハードルが高いのも事実…。
この「超音波でわかる運動器疾患−診断のテクニック」は、各関節の描出方法が分かりやすく解説されています。



エコーを学ぶなら持っておくべき一冊!
まとめ:整形外科疾患のリハビリでおすすめの書籍10選


本記事では運動器疾患のリハビリを行う上で、筆者自身が本当に役に立ったなという書籍を10冊紹介しました。
どれも自信を持ってオススメできるので、是非参考にしてみて下さい!
今回は以上です!











